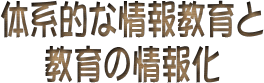|
|
| ◆ 文部省(現文部科学省)等の動き |
・21世紀を展望した我が国の教育の在り方 平成8年7月中央教育審議会第1次答申 |
| 「教育と情報化」の章を設けて、情報教育の体系的な実施、情報機器・情報通信ネットワークの活用による教育の 質的な改善・充実、高度情報通信社会に対応する「新しい学校」の構築、情報化の「影」の部分へ対応する必要性を 指摘している。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701.htm |
・情報化の進展に伴う初等中等教育における情報教育の推進等に関する関係協力者会議 平成10年8月最終報告 |
| 情報教育の目標を情報活用能力の育成と捉え、その情報活用能力を 「情報活用能力=情報活用の実践+情報の科学的な理解+情報社会に参画する態度」 と3本の柱で規定した。 小・中・高一貫した情報教育の在り方について、「情報活用能力と生きる力との関連性、発達段階や各教科等の学習 との連携に留意しながら、3つの柱の関連性やバランスに配慮した系統的、体系的なカリキュラムを編成する必要があ ると述べている。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/002/toushin/ |
・情報化への対応の在り方 平成10年7月教育課程審議会答申 |
| (情報化への対応の部分抜粋) 今後、ますます高度情報通信社会が進展していく中で、児童生徒が、溢れる情報の中で情報を主体的に選択・活用 できるようにしたり、情報の発信・受信の基本的ルールを身に付けるなど情報活用能力を培うとともに、情報化の影響 などについての理解を深めることは、一層重要なものになってくると考える。 現在、情報に関する教育については、小学校段階で教具としての活用を通してコンピュータに触れ慣れ親しむことを 基本とし、中学校段階で技術・家庭科の選択領域「情報基礎」においてコンピュータの役割や機能を理解させ、情報を 適切に活用する基礎的な能力を育成するとともに、中学校及び高等学校において数学、理科、家庭科でコンピュータ の原理等を扱うこととされている。 平成11年度までに公立学校において、小学校で2人に1台、中学校・普通科高等学校・盲学校・聾学校・養護学校で 1人に1台の水準で教育用コンピュータの整備が進められている。また、学校における情報通信ネットワークについては、 中学校・高等学校・盲学校・聾学校・養護学校は平成13年度までに、小学校は平成15年度までに、すべての学校が インターネットに接続できるよう計画的な整備が進められている。 今後は、児童生徒の発達段階に応じて、各学校段階を一貫した系統的な教育が行われるよう更に関係教科等の改善 充実を図り、コンピュータや情報通信ネットワーク等を含め情報手段を活用できる基礎的な資質や能力を培う必要があ ると哉考える。 具体的には、小学校、中学校及び高等学校を通じ、各教科等の学習においてコンピュータ等の積極的な活用を図る こととし、学校段階ごとには、小学校においては「総合的な学習の時間」をはじめ各教科などの様々な時間でコンピュータ 等を適切に活用することを通して、情報化に対応する教育を展開する。中学校においては技術・家庭科の中でコンピュータ の基礎的な活用技術の習得など情報に関する基礎的内容を必修とし、高等学校においては、情報手段の活用を図りなが ら情報を適切に判断・分析するための知識・技能を習得させ、情報社会に主体的に対応する態度を育てることなどを内容 とする教科「情報」を新設し必修とすることが適当である。 なお、情報に関する教育の推進に当たっては、人間関係の希薄化や実体験の不足の招来など、情報化が児童生徒に 与える「影」の部分に十分留意することが望まれる。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shingi/index.htm |
・学習指導要領の告示 平成10年12月14日 幼稚園教育要領,小学校及び中学校学習指導要領 平成11年 3月29日 高等学校学習指導要領,盲学校,聾学校及び養護学校幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領,高等部学習指導要領 |
| http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youryou/index.htm |
新学習指導要領は,幼稚園については平成12年度から全面実施し,小・中学校については平成 14年度から全面実施し,高等学校については平成15年度から学年進行で実施し,盲・聾・養護学校 については,幼,小,中,高の各学校段階に準じて実施することとしています。 また,完全学校週5日制については,平成14年度から,すべての学校段階一斉に実施することと しています。 |
◆ 教育の情報化を推進する施策と事業 |
・バーチャルエージェンシー「教育の情報化プロジェクト」 平成11年12月報告 |
| http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/12/991210f.htm |
| バーチャルエージェンシーとは、既存の枠組みにとらわれない新たな推進体制として、平成10年12 月に組織された内閣総理大臣直轄の省庁連携タスク・フォースのことであり、「教育の情報化プロジェ クト」は、4つのプロジェクトのうちの一つです。 |
・ミレニアムプロジェクト 平成12年1月 |
教育の情報化 2001年度までに、全ての公立小中高等学校等がインターネットに接続でき、すべての公立学校 教員がコンピュータの活用能力を身につけられるようにする。さらに、2002年度には、我が国の教 育の情報化の進展状況を、国際的な水準の視点から総合的に点検するとともに、その成果の国 民への周知を図るため、国内外の子供たちの幅広い参加による、インターネットを活用したフェス ティバルを開催する。 2005年度を目標に、全ての小中高等学校等からインターネットにアクセスでき、全ての学級のあ らゆる授業において教員及び生徒がコンピュータを活用できる環境を整備する。 ミレニアム・プロジェクトのプロジェクトのテーマより http://www.kantei.go.jp/jp/mille/index.html |
・ミレニアムプロジェクト「教育の情報化」の解説 |
文部科学省生涯学習局のホームページ( http://www.manabinet.jp)から、PDF形式のファ イルで入手できます。 この解説書は、2000年度(平成12年度)から開始されているこのプロジェクトについて、教育委 員会や学校などの関係者に正しい理解を持っていただき、我が国教育の情報化の健全な進展に資 することを目的として、文部省学習情報課で作成されたものです。 |
| ◆ 21世紀教育新生プラン 平成13年1月 学校、家庭、地域の新生〜学校が良くなる、教育が変わる〜 ・IT 関連部分抜粋 授業を子どもの立場に立ったわかりやすく効果的なものにする。 IT 教育の促進 − 教育の情報化(ミレニアムプロジェクト)の目標の実現 −平成17年度までに 全ての小中高等学校等からインターネットにアクセスでき、全ての学級のあらゆる授業において教員及び生徒が コンピュータを活用できる環境の整備 *1台当たり生徒児童数 13人(平成12年3月) → 5.4人(17年度) IT 授業や 20人授業のための「新世代学習空間」の整備 参考 レインボープラン<7つの重点戦略> 「21世紀教育新生プラン」をよりわかりやすく説明した資料はここを http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/21plan/index.htm |