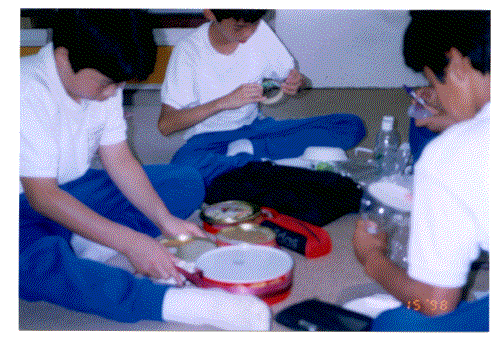環境教育講座資料 教科・音楽
1 題材名 「曲想豊かなアンサンブルの工夫」(中学校1年)
2 題材のねらいと環境教育の関連
(1) 題材のねらい
・いくつかの違ったリズムを重ねることで音の重なりのおもしろさを体感できる。
・強弱の変化をつけることで、表現の楽しさ、美しさを味わうことができる。
・自分の願う音の出る楽器を製作することで、音の美しさを感じることができる。
・遊びながらリズムをとることから出発し、楽譜を見ながらリズムをたたくことができる。
・仲間とアンサンブルをする中でできる喜びを味わい、学習に意欲的に取り組むことができる。
(2) 教材観
「打楽器のための小品」は、6つのパ−トで構成された旋律のない音楽である。また,躍動感、 緊迫感を味わうことのできる教材でもある。生徒の好む音楽を聞くと、旋律の流れや歌詞の内容よりも直 感的にのりのよい曲を好み、そこにはリズムが優先しているように感じられる。このことからリズムに対 して敏感である生徒たちのよさを生かせる教材あると考えた。
太鼓の類は、原始時代から存在するもので、ほとんど世界中のすべての民族がこれを持ってい ると言われている。人間は体内にも心臓のリズムがあり元来,本能的にたたいてリズムをとることを好む と考えられる。そこで、旋律のないリズムだけの音楽に触れさせることによって、身体からわき起こる音 への楽しさを味わわせたいと考えた。また、自分だけの打楽器を製作することを通して、自分の願う音、 美しい音にこだわる態度を育てたいと考えた。自分たちの生活の中から美しい音を見つけだすことや探す ことが環境教育のめざす豊かな感受性と表現活動につながるはずである。
3 本時のねらい
自分たちの身の回りのものから、自分の願う美しい音を出すことができる打楽器を製作し、 その音色の美しさを味わうことができる。
4 環境教育上の工夫・配慮
本校の校区は、岐阜市に隣接しており、市街地に属される地域もある一方で、生徒たちが 川遊びをしたり、自然に触れ合うことのできる山があるという特色がある。生徒は、こういった環境 の中で、守られている自然と破壊されていく自然の両面を体験しているわけである。
そこで、五感を通して感じることが環境教育につながると考えた。楽器をつくることで、 耳を通して「自分の望む音色」「他の音色をの重なり」を感じ、創造することができるはずである。 また、楽器づくりを通して、身の回りにあるものでも美しい音がでるということを体感すると考えた。 そのため、楽器の材料に工夫をさせ、より美しい音色、自分の望む音色に近づけるよう助言・支援をした。
5 指導計画
| 節 | 時 | 学 習 内 容 | 興味関心 | 知識技能 | 態度行動化 | 環境教育に関するねらい | |
| 1 | 1 |
リズムを楽しもう。 ・「蛍」の歌詞にリズムをつけ、リズム打ちをする。 ・「蛍」のリズム ・カノンをする。 | 〇 | 自分の身体でリズムを感じて表現できる。 | |||
| 2 | 2 |
自分に合った方法で、他のパートを覚えよう。 ・テ−プに合わせて正しく表現できるよう練習する・他のパ−トのテ−プと合わせて練習する。 ・全体で合わせる。 | 〇 | 〇 | 自分の身体でリズムを感じて表現できる。 | ||
|
3 |
音の重なりを感じよう。 ・グル−プ練習をする。 ・全体で合わせる。 |
| 〇 |
| 6つの音の重なりのおもしろさを感じることができる。 | ||
| 4 |
強弱の変化をつけよう。 ・グル−プ練習をする。 ・強弱の変化を工夫する。 ・たたき方を工夫する。 |
| 〇 | 強弱の変化を身体で感じることができる。 | |||
| 5 |
6つのパートの重なるおもしろさを聴こう。 ・前時までの学習を振り返り、交流会をする。 ・全体で合わせる。 | 〇 | 〇 | いろいろなグル-プの発表を聴き、音の重なりや強弱の変化のおもしろさを味わうことができる。 | |||
|
3 | 6 |
自分の打楽器を作ろう。 ・自分の出したい音の出る打楽器を製作する。 | 〇 | 〇 | 音の重なりのおもしろさを意識した打楽器をつくることができる。 | ||
| 7 |
打楽器の音の重なりを楽しもう。 ・打楽器を使ってグル−プ練習をする。 ・それぞれの楽器の音を生かして、表現を工夫する。 | 〇 | 〇 | 違った材質の打楽器の音の重なりのおもしろさを感じることができる。 | |||
|
8 |
仲間の表現を学び合い、リズムを体で楽しもう。 ・前時の学習を振り返り、交流会をする。 ・全体で合わせる。 |
〇 |
〇 |
| いろいろな打楽器の音の重なりや強弱の変化のおもしろさを味わうことができる。 |
| 過程 | 主 な 学 習 活 動 |
指導上の留意点 (環境教育上の工夫・配慮) |
|||
|
導入 展開 終末 |
○グル−プごとに「打楽器のための小品」を合わせる。 ・拍を感じながら合わせる 。 |
・リズムや音の重なりを身体で感 じることができるよう、拍を数え ながら合わせる。 ・事前から自分の願う音の出る材料を探すように話しておく。 ・材料の違いによる音色の違いがわかるように示す。 ・より美しい音色が出せるよう助言する。 ・それぞれの楽器のよさや美しい音色に気付いている生徒を紹介し、よさを広める。 ・それぞれの楽器の音色の面白さ、美しさを聴くよう助言する。 |
|||
| 本時の課題 | |||||
| 自分の願う音の出せる打楽器を製作しよう。 | |||||
|
○材料によって音の感じが変わることを明らかにする。 ・木材 ・竹 ・金属 ・プラスティック ・ガラス ・紙 など ○自分の楽器の製作をする。 願いに合った音の出る楽器を工夫して、製作する。 ○自分の楽器で演奏してみよう。 ・願いに合った音に近づいたかどうかを確かめる。 ・グル−プごとにお互いの楽器の音を聴き合い、よさを見つけ合う。 ○自己評価 ・プリントに自分の楽器の音について、工夫についてなどを記入する ○次時の予告 ・製作した楽器を使って、グル−プごとにアンサンブルをする。 |
|||||