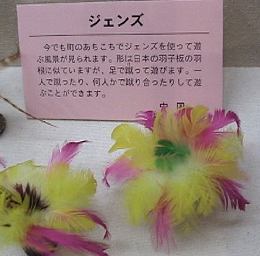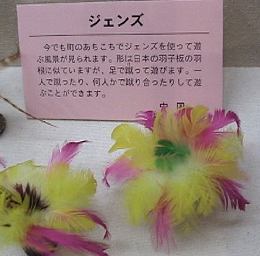
中 国「ジェンズ」
世界で一番使われている言葉をご存じですか。英語でしょうか。いいえ、中国語です。中国の人口は実に世界の20%を占めるからです。面積は世界第3位。また、世界最古の歴史を持ち合わせ、首都北京には歴史的建造物と共に現代的なビルが建ち並ぶ活気にあふれた街です。
中国と日本との関わりは古く、宗教や生活習慣で中国から取り入れられたものが多く見られます。漢字も中国から伝わったものであり、故事成語として私たちが慣れ親しんでいる中国の話は、現代の中国人より多いのではないかと思う程です。文化大革命で否定された寓話や神話が最近では見直され、絵本などになって出版されるようになりました。そこには初めて見る話が多く、日本に伝わった話はほんの一部に過ぎないことがわかります。
また、思いがけないもので中国から伝わったのではないかと考えられるものがあります。例えば、ジェンズです。ジェンズは北京の街のあちらこちらで見られる遊び道具です。足首や足の甲・裏を使って蹴り上げます。一人で何回か続けて蹴ったり、何人かで羽根が落ちるまで蹴り合ったりして遊びます。人数や場所に制約されない使い勝手の良さが特徴です。ジェンズを見ると日本の羽根つきの羽を思い浮かべませんか。日本では見られなくなった羽根つきですが、ジェンズから変化して伝わったのではないかと考えるのも楽しいものです。
ただ、これ程関わりの深い中国ですが、唯一深い陰があります。戦争の傷跡です。抗日戦争記念館は、字のごとく日本軍に抵抗した戦士たちの姿を記念して建てられました。日本軍の北京侵略の象徴である、盧溝橋の近くに建っています。日本では原爆や空襲や生活苦を通して語られる戦争が、中国では日本軍の侵略とそれへの抵抗として語られています。この記念館を訪れ、「過去から学んで未来に生かそう」という言葉が掲げられているのを見ると、様々な感慨が心をよぎります。
日本と中国は「一衣帯水」の間柄です。日本にとって中国はやはり大きな存在だと言えましょう。(小島 恵子)
中国の展示品
 |
:空竹(中国独楽)
:真ん中のくぼんだところに紐を引っかけ、空中で独楽を回します。速く回すと独楽から音がしてきます。上級者になると音がし始めた独楽を空中に投げ、紐で受け止めることができるようになりますが、音が出るまで回せるようになるのには、相当練習しなければなりません。
|
 |
凧
:北京では、あちらこちらで凧をあげている人がいます。秋から春にかけて天安門広場は言うまでもなく高架橋でも凧あげを楽しんでいる人がいます。
|
台湾「先住民」の人々との出会い
粘板岩で造られた家(台湾) 
高雄日本人学校勤務の3年間(昭和60〜62年度)、先住民と呼ばれる、かつて日本人が高砂族と呼んだ人々との忘れられない出会いがありました。淡褐色の膚、大きく輝く目、二重まぶた、やや低い身長、9部族に分類されるという先住民の集落を訪れると、台湾にあって異国に来たのではと錯覚を起こしてしまいそうな人々の生活がありました。
最初に出会ったルカイ族、パイワン族の人々は、屋根や壁、床に厚さ1〜2センチから数センチの粘板岩を使った家に住んでいました。1年を通じて訪れてみると、冬は暖かく夏は涼しい快適な住まいでした。他の部族には、竹や茅造り、木造の家があり、各部族の伝統住宅はその地に産する材料で造られていることがわかります。
食事は「ゆでる」「やく」に限られ、調味料も塩、唐辛子、生姜、それに蜜くらいしかなく、味は淡泊です。塩は貴重品であったと思われます。主食は雑穀やタロイモなどのいも類ででした。
山深い霧社には「抗日戦英雄の碑」があり、日本の統治時代を思い出させます。しかし、「日本人と出会うのは何十年ぶりのことか」と涙する人と出会い、強制的に学習させられた日本語が、各部族の共通のコミュニケーションの手段になっていることを知り、さらに、不衛生な生活習慣を改めるようにと日本人が教えてくれたとの語りにふれると、中国の諺「有縁千里来相会」を思います。
先住各民族の文化は日増しに変化してきていると言われています。しかし、山地に定住後、環境に適応しながら漢民族とは異なる文化・生活様式を守ってきた人々との出会い、そして訪れるたびに精一杯の接遇をしてくれた先住民の人々とのふれあいは、今も心の奥底に深く深く刻み込まれています。
(田村二三男)
台湾の展示品
 |
先住民の帽子 |
 |
中国結び
今では現地ではあまり流行っているとはいえない中国結びだが、中国の伝統を伝えるものとして外国人が作り方教室に参加し色々な作品を作っている
現地の人に言わせてみればちょっと古くさい感じらしい
専用の紐があるが、普通の紐でもいいのでどんな風に1本の紐から作品が作られていくのか辿ってみるのも面白い
|